骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症とは?
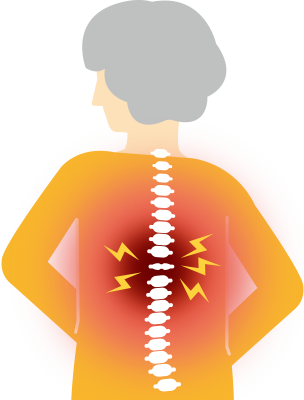
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の密度が低下し、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。特に閉経後の女性や高齢者に多く見られ、加齢に伴い骨の新陳代謝が低下することで発症します。骨粗鬆症は初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、転倒や軽い衝撃でも骨折しやすくなるのが特徴です。
また、橈骨遠位端骨折(手首の骨折)などの骨折後には、骨粗鬆症治療を早期に開始することが重要です。骨折がきっかけで骨粗鬆症が見つかるケースも多く、適切な治療を行うことで、さらなる骨折を予防できます。
骨粗鬆症の原因
✅ 加齢(骨の新陳代謝の低下)
✅ 閉経によるホルモンバランスの変化(エストロゲンの減少)
✅ カルシウム・ビタミンD不足
✅ 運動不足(骨への適度な刺激が少なくなる)
✅ 喫煙・飲酒(骨密度の低下を促進)
✅ ステロイド薬の長期使用
骨粗鬆症によるリスクと症状
骨粗鬆症は「沈黙の病気」とも呼ばれ、自覚症状がほとんどありません。 しかし、進行すると以下のようなリスクがあります。
骨折しやすくなる
- 転倒や軽い衝撃で骨折しやすくなる(特に背骨・手首・大腿骨)
背中や腰の痛み
- 背骨の圧迫骨折により、腰や背中に慢性的な痛みが発生
身長が縮む・姿勢が悪くなる
- 背骨の変形(円背:猫背)**が進行し、身長が低くなる
要介護のリスクが高まる
- 大腿骨近位部(股関節)骨折をすると、歩行が困難になり、寝たきりの原因になることも
骨粗鬆症の診断方法
当院では、高精度なDXA(デキサ)法による骨密度測定機器を導入しており、より正確な診断が可能です。
DXA法の特徴
✅ X線を用いた測定で、精度が高く信頼性がある
✅ 腰椎(背骨)や大腿骨の骨密度を詳細に測定できる
✅ 骨折リスクの予測が可能
その他の検査
✅ 血液検査(カルシウム・ビタミンD・骨代謝マーカー)
✅ レントゲン検査(骨折や骨変形の確認)
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が基本となります。
生活習慣の改善
✅ カルシウム・ビタミンDを十分に摂取する(乳製品、小魚、きのこ類など)
✅ 適度な運動をする(ウォーキング、軽い筋力トレーニング)
✅ 日光を浴びる(ビタミンDの生成を促進)
✅ 喫煙・過度の飲酒を控える
薬物療法(医師の指導のもとに実施)
骨吸収を抑える薬
✅ ビスホスホネート製剤(骨の破壊を防ぐ)
✅ SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)(閉経後の骨密度低下を抑制)
✅ 抗RANKL抗体(骨吸収を抑え、骨折予防に有効)
骨の形成を促進する薬
✅ 副甲状腺ホルモン製剤(PTH製剤)(骨形成を促し、骨密度を増加)
✅ 抗スクレロスチン抗体(新しい骨形成促進薬で、骨折予防に効果的)
カルシウム・ビタミンD補充
✅ カルシウムとビタミンDの補充で、骨の健康を維持
患者様の年齢・性別・骨密度・骨折歴・他の疾患の有無などを考慮し、最適な治療を選択します。
骨折後の骨粗鬆症治療の重要性
橈骨遠位端骨折(手首の骨折)や脊椎圧迫骨折を起こした後は、骨粗鬆症の進行が疑われるため、早期の治療が重要です。
なぜ骨折後に治療を始めるべきか?
✅ 骨折を繰り返すリスクが高い(二次骨折予防が必要)
✅ 骨折がきっかけで要介護状態になる可能性がある
✅ 適切な治療で骨密度を改善し、再発を防げる
当院では、骨折後の患者様にも積極的に骨粗鬆症検査を行い、必要に応じて治療を開始します。適切な予防策を講じることで、患者様の健康を守ることに努めています。
まとめ
骨粗鬆症は、自覚症状がないまま進行し、骨折のリスクを高める病気です。 特に、手首・背骨・大腿骨の骨折は寝たきりにつながる可能性があるため、早期の検査と治療が大切です。
当院では、DXAによる高精度な骨密度測定が可能で、骨粗鬆症の早期発見・治療を行っています。 また、橈骨遠位端骨折(手首の骨折)などの骨折後には、骨粗鬆症治療を開始することで、さらなる骨折を予防することが重要です。
「骨密度が気になる」「家族に骨粗鬆症の人がいる」「最近背が縮んだ気がする」といった方は、ぜひお気軽にご相談ください。

